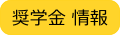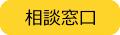あの日から100日、テレビは犠牲者慰霊祭の様子を放映していました。遺族代表が「夢であってほしかった」と穏やかに語り、故郷の復興を願って気丈に言葉を紡いでおられる姿を目にし、胸が一杯になりました。 人を思い遣る優しい気持ちを育んでほしいと、生徒会顧問に復興支援ボランティアを企画していただき、希望者を募って先日派遣しました。西原村に向かう途中、ブルーシートがかぶさったり、崩壊し傾いたりした家々を目にしたはずです。被害がほとんどなかった天草の子どもたちは、この厳しい現実をどのように受け止めたのでしょうか。帰校を出迎えはしましたが、炎天下の作業でぐったりと疲れ果ててバスを降り立つ生徒を見て、聞くことが憚られました。
セミの鳴き声が儚く聞こえるこの季節は、戦争と戦後を考える日々とも重なります。私が教師になりかけの頃は、グラマンから受けた機銃掃射など少年時代の恐怖の体験を実習の点呼時等に熱く語りかける先輩教師がいました。しかし、今では子どもたちは勿論、教師も戦争を知らない世代ばかりとなり、原爆、特攻、空襲、抑留などと聞いても、悲しく苦しい響きを伴う言葉としての認識しかできません。
地震にしろ戦争にしろ、何もしなければどんどん風化し、多くの人たちにとって歴史の一コマになるのは避けられません。そう言えば、終戦後や東日本大震災直後に多くの人たちに共感をもって読み返されたという方丈記、この中の元暦2年(1185年)、平安京を襲った大地震について述べたくだりの最後が次の趣旨の記述で締め括られていたのを思い起こします。
「その直後には、誰もかれもがこの世の無常とこの世の生活の無意味さを語り、いささか欲望や邪念の心の濁りも薄らいだように思われたが、月日が重なり、何年か過ぎた後は、そんなことを言葉にする人もいなくなった」 人の性(さが)の常とはいえ、800年前の人たちもそうだったのだと思うと、身につまるものがあります。
悲惨な経験や悲しみを繰り返してはいけないということ、風化させてはいけないということを、親から子へ、子から孫へどう伝えていくか、そのシステム作りも含め教育の力に待たれるわけで、私たち教育に携わる者は心静かに模索する日々が続きます。 校長
  |