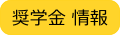 |
 |
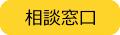 |

3日前、出張で熊本に向かっていたら、ラジオから「クリスマスをお題にした折句を募集します」と聞こえてきました。「えぇ?折句ってラジオで普通に募集するほど有名で、そんなに簡単にできるの?」と半信半疑で聞いていました。生徒の皆さんは「折句」を知っていましたか? この場合、簡単に言えば、五七五七七のそれぞれの頭にクリスマスという5文字を折り込めというものです。その番組では次の一首を例示していました。 薬指 リングをそっと 滑らせて まだあと5分 少し泣きたい くすりゆび りんぐをそっと すべらせて まだあとごふん すこしなきたい このリング、どちらに滑らせているのでしょうか?外す方向なら何ともやるせない歌だな~とか思いつつ、そういえば、俵万智さんの短歌集の中にも一首、折句が紹介してあったことを思い出し、帰ってから本を引っ張り出しました。次の歌は田中章義さんという十代の歌人の予備校時代の作品なんだそうです。 クリスマスりんりん響く鈴の音を全く無視してスタディーハード キーワードを隠すたわいもない言葉遊びのようですが、いざ作るとなるとそれがどうしてとても難しいのです。高校の時、伊勢物語の中で折句を学んだ際に、恋の機微にすっかり高揚した大学出たての若い先生が「なつやすみをお題にした折句の歌を作ってらっしゃい」と宿題にしたので、やってみたことがあります。 ……ん~。………んっ!?……ん~ん。………はぁ といった感じで、2~3時間格闘しましたが結局できませんでした。 折句に限らず、すべての仮名を一文字ずつ使ったいろは歌やショパンの黒鍵のエチュード(右手がピアノの黒い鍵盤だけを弾く曲)もそうですが、こういう技巧がすらすらできる人って一体どういう頭をしているんだろうとホントに感心・感服してしまいます。だから、ラジオでアナウンサーが「いつでもどこでも、眠れない時、眠りながら、歩きながら、雨を見ながら、待ち合わせの間にも作れますよ!」と、いとも簡単な感じで喋っておられるのを聞き、「本当かな~?」って思った次第です。 ところで、私の「折句」との出会いは、前述のように平安時代きってのプレイボーイ、在原業平の自伝的物語とされている伊勢物語の授業中です。ネットで改めて調べてみたらまさしく次のようなお話で、それを習った頃の教室の匂いまで懐かしくよみがえりました。 昔、ある男(=在原業平とおぼしき主人公)が都への未練を残しつつ関東の方への旅を続け、三河の八橋(今の愛知県知立市のあたり)に着いた。その沢のほとりの木蔭に馬から降りて座って、乾飯(かれいひ:水やお湯で戻して食べるドライライス)を食べた。 その沢に、かきつばた(菖蒲やあやめに似た植物)がとてもきれいに咲いていた。それを見てある人が、「かきつばたという五文字を各句の頭に置いて、旅の心情を詠みなさい」と言ったので、男が次のような歌を詠みます。 からごろも きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる たびをしぞおもふ (現代語訳:着て馴れ親しんだような妻が都に居るものだから、はるばるとこんなに遠くまで来てしまった旅を悲しく思うのです) 最後に、乾飯の上にポロポロと涙が落ちて、乾飯はふやけてしまったのだった、という何とも切ない落ちまでつくという物語です。 「切ない」で思い出しましたが、クリスマスの俳句として次の句を新聞の歌壇面で目にし、「そういうこともあったよな・・・」と中島みゆきの「時代」よろしく胸が一杯になったことがありました。 行くあての ないクリスマス 髪を切る HPバナーでは、クリスマスの贈り物やメッセージ交換が話題になっていましたが、皆さん方もクリスマスにちなんで、折句に挑戦するなり、一句ひねって恋心を歌に託して相手に贈ってみませんか。 そうそう、作った句は今のあなたの青春の一頁です。大事に保管しておきましょう。 |