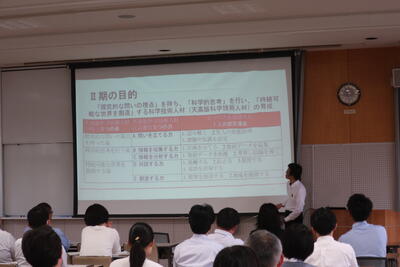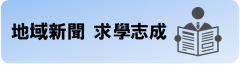タグ:評価
【ASⅢ】研究&アブスト&ポスター&more... / So Many Things To Do!
ASⅢの生徒たちは先週仮評価も終わり、久々にじっくりと研究活動を行っています。とはいえ、研究を進めるだけではなく、サイエンスインターハイのアブストラクト作成や、探究成果発表会に向けたスライドやポスターの準備など、やることがたくさん! それぞれ思い思いに、かつ、着実に研究を進めているようです。
さて、地学室では、久々にヘドロ入りバケツを手にした「汽水域班」を発見しました。採取直後に測ったBOD(生物化学的酸素要求量)と、採取して1週間たったヘドロのBODを比較することで、微生物の代謝活動を調べているそうです。その後ろには、「魚糞班」が金魚の水槽から魚糞を採取しているのが見えます。また、2年生に混じって「農業班」の3年生の姿が! 2年生の生徒にアドバイスしているようです(頼もしい!)。
今日は、あちこちで研究活動をしている12班全てを写真に収めてみました。みんな楽しそうに頑張っています。忙しい3年生ですが、研究も勉強も総体も総文もファイトです!
農業班 魚糞班 汽水域班
音班 走り班 精油班
「つなぐ」班 バイオマス発電班 化石班
消波ブロック班 電磁誘導班 イシクラゲ班
After the provisional evaluation last week, students in AS III are enjoying their research again. Each of them seems to be moving forward with their research activities thoughtfully and steadily. However, that’s not the only thing they need to do - they also have a lot of other work to do, such as preparing abstracts for the “Science Interhigh” and preparing slides or posters for their presentations in July.
Now, in the Earth Science room, we found the “Brackish water group” with a bucket of sludge in their hands! They are studying the metabolic activity of microorganisms by comparing the BOD (Biochemical Oxygen Demand) measured immediately after collection of the sludge and the BOD after one week. Behind them, the group “Fish Waste” can be seen collecting fish waste from a goldfish tank. Also, among the second-year students is a third-year student from the “Agriculture” group! He seems to be advising the second-year students - how nice!
Above you can see the pictures of all ASⅢ 12 groups doing research in class. They all looked like they were having fun and working hard. They are such busy 3rd graders, but they are all doing their best in everything!
【ATⅡ】仮評価を行いました / Tentative Evaluation Today
本日のATⅡでは、C2「考察し結論を導く」の仮評価を行いました。各班、現在の状況や本評価までに進めなければならないことについて、班員同士や担当者とのディスカッションを熱心に行っていました。
本校ではルーブリックを活用して課題研究の評価を行っており、その中でディスカッション形式で実施する「仮評価」と、個人面談形式で実施する「本評価」を実施しています。本時実施した仮評価は、生徒本人と担当者が現在の状況を客観的に見て、研究の深化のために今後どのように動いていかなければならないのかを考える機会でもあります。現時点で目標が達成できていない場合には、達成のための具体的な手立て(実験や調査)を考え、実行することで研究の質を高めることができるはずです。
今日の仮評価では、思ったより自分たちの研究が進んでいないことに気づき、慌てて実験や調査の計画の見直しをする班も目立ちました。今回の評価では仮説の検証が1つのポイントにもなっていますが、検証の仕方にももう少し工夫が必要な班もあるようです。明日からは中間考査も始まり忙しい3年生ですが、時間の使い方を工夫して、研究活動もがんばってください!

A tentative evaluation of “C2”: "Consider and Draw Conclusions" was conducted in today’s ATⅡ. Each group was enthusiastically discussing with each other and their teachers about their current situation and what they need to proceed with before the main evaluation planned in June.
In our school, we use a rubric to evaluate research projects, which consists of "tentative evaluations" conducted in a discussion format and "main evaluations" conducted in the form of individual interviews. The tentative evaluation is an opportunity for the students themselves and the teachers in charge to look at the current situation of the research objectively and consider how they need to move forward to deepen their research. If they haven’t reached their goals at this point, students need to consider and implement specific steps (experiments and investigations) in order to achieve their goals with the time given until the main evaluation.
In today's evaluation, some of the groups seemed to realize that their research was not progressing as well as they had expected, and they had a chance to revise their plans for experiments and surveys. Verification of hypotheses is one of the key points of this evaluation, but it seems that some teams still need to consider the way they verify their hypotheses. The students will be even busier since mid-term examinations will begin tomorrow, but, to the students: please use your time wisely and do your best in your research activities too!
【SSH】職員研修を行いました
本日、午後からの職員研修の1つとして、課題研究評価に係るSSH職員研修を行いました。
まず、SSH研究主任より、本校のSSH事業や教科間連携、指導と評価を一体化した課題研究指導についての説明がありました。その後、ワークショップを行いました。今回の活動では、本校で設定している「13の探究場面」のうち、A1(読み解く)を題材とし、AS(天草サイエンス)およびAT(天草探究)の授業の評価で使用する「質疑による評価シート」を用います。まずは、ある架空のディスカッションの動画を見て、生徒(※天高職員が生徒役です)の発言を観察し、それぞれの生徒の現時点でのA1(読み解く)の到達度を考えました。その後、グループで意見を出し合い、協議を行いました。
研修を通して、仮評価は「評価」としての側面だけではなく、生徒たちにとって、自分たちの到達度を把握し、今後の研究の進め方を考えるための「指針」としての側面を持つことを学びました。また、課題研究においては、教師が「指示」や「指導」ではなく、「問いかけ」をすることで生徒の気づきを促し、研究の深化をサポートしていく必要性も再確認することができました。
天草高校がSSH指定を受けてから8年目となりました。本校では、これからも全校体制で課題研究を充実させ、授業改善を行い、外部連携を行いながら生徒の探究的な学びをサポートしていきます。SSH関連の様々な活動に関して、授業内外での生徒たちの頑張りをご覧いただき、応援していただけると嬉しいです。