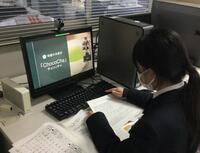学校生活
2022/02/08 生徒考案チョコレート販売スタート
7月に、くまもと県南フードバレー推進協議会主催の商品開発コンテストにおいて、商品化が決定した「Chococha(チョコッチャ)」がついに発売されました!
これは、令和2年7月豪雨災害からの復興とコロナ禍において、「人吉球磨地域を応援したい」という高校生の思いを形にしたものです。株式会社 KASSE JAPAN様が試作から販売までご協力いただきました。
チョコッチャは人吉球磨産の、抹茶、番茶玄米、ほうじ茶、玉緑茶、ほうじ茶玄米、番茶を使用した6種類のチョコレートです。玉緑茶は熊本県が日本一の生産を誇っています。県内でも人吉球磨が最大の生産地です。お茶の風味が十分に味わえる、とても濃厚なお茶チョコレートとなっています。皆様、ぜひお買い求めください!!
販売場所:人吉温泉物産館
HASSENBA
立山商店
八代よかとこ物産館
SAKURAMACHI Kumamoto地下1階旬彩館さくら
販売価格:1箱 800円(税別)
在宅のオンライン授業時も頑張っています
分散登校となり3週目となりました。生徒たちは、出席番号の奇数、偶数で一日おきに登校していますが、学校への登校がない日は、家庭でのオンライン授業に取り組んでくれています。当初は、ネットワークの関係等でなかなか苦慮する面もありましたが、今では生徒たちも、先生たちも随分と慣れて、スムーズに授業が進められるようになっています。
家庭でのオンライン学習では、学校と同じ日課で一日を過ごすことになります。朝の登校には、時間的なゆとりがありますが、8時30分からは制服に着替えてのSHRから一日をスタートさせます。今日登校の日だった、1年生商業科の女子の生徒たちと話をする機会がありました。オンラインの授業にも随分と慣れてきたとのこと。また、昼食後の掃除の時間には、自分の部屋をしっかりと掃除していますと、力強く答えてくれました。家でのオンラインの授業時にも、学校と同じように基本的な生活習慣をしっかりと守り過ごす、本校生徒の素晴らしさを改めて痛感した会話でした。
凜とした朝に
今朝の錦町の気温は、-2度。
凜とした空気が頬に刺さります。
写真は、朝8時過ぎの校舎ですが、
朝早く登校した生徒たちが廊下の窓を開け、
空気の入れ換えをしてくれています。
本当ならば、こんな寒い朝に窓を開け放ちたくはないですよね…
でも、寒さを我慢しながらコロナ禍における
適切な対応を取ってくれていることに安堵を覚えます。
2022/02/04 熊本県簿記検定委員会及び簿記会計研究部会
商業科、情報処理科の生徒が学ぶ「簿記会計」に関する会議が、球磨中央高校を本部校として開催されました。熊本県で簿記会計を指導される先生方が、検定や簿記の大会、指導方法などについてオンラインで話し合われていました。
2022/02/02 生徒考案チョコレート事例発表リハーサル

今年度、くまもと県南フードバレー主催の商品開発に応募し、商品化が決定した「ChocoCha(チョコッチャ)」の取組事例発表が2月9日(水)にオンラインで開催されます。
3年生の登校日に併せてリハーサルを実施していただきました。初めてのリモートでの発表で、画面操作をしながらで緊張しています。当日は多くの企業の方々や副知事にも聞いていただきますので、商品化への想いや商品化の過程をお伝えし、人吉球磨の新たなお土産品となるよう力を尽くします。