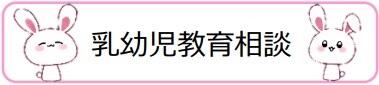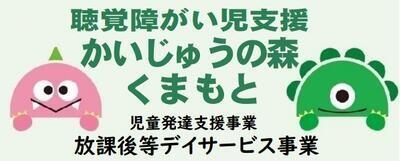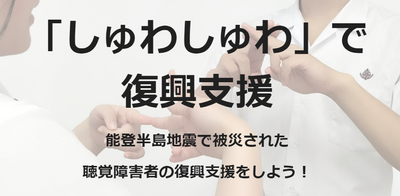校長室からの便り
「くまろう祭」を終えて
11月30日(土)、令和元年度「くまろう祭」は多くのご来賓、ご家族、卒業生、そして関係団体のご臨席とご協力を得て、無事終了しました。
今年度は、くまろう祭テーマ「心を一つに前へ!新たな物語に~令和の序章~」のもと、各学部等からのステージ発表、そして展示を中心に催しましたが、その随所に子供たちのひかり輝く個性を見ることができ、大変うれしく思いました。
本番に至るまでには、楽しいことだけではなく、それぞれに壁にぶつかったこと、悩んだこと、苦労して作り上げたこと等があったかと想像します。しかし、それらを乗り越えながら、子供たちは確実に一歩前へと踏み出すことができたと思います。それぞれの経験をバネにして、自分に自信をもってこれからの学びにつなげていってほしいと願っています。
また、小学部のたんぽぽ学級の発表は欠席のお友達が増えたため、ビデオ上映に変える形になりましたが、皆さんの日ごろの頑張りの様子が伝わってきました。日を改めて、みんな揃ってのお披露目の機会があることを期待します。
結びになりますが、当日朝早くからお出でいただいたご来賓の皆様をはじめ、ご家族の方々、ご参観いただき誠にありがとうございました。
併せて、「くまろう祭」をバザーで盛り上げてくださったPTA役員の方々、本校高等部就労コースの生徒作品製作にご協力をいただいた熊本はばたき高等支援学校の皆様、そして、展示等にご協力いただきました県ろう協青年部及び難聴協会青年部の皆様本当にありがとうございました。今後とも本校へのご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
さあ、幼稚部から高等部までの皆さん…次の目標に向かって、また今週からの学校生活を充実したものにしていきましょう。
台風15号から学んだこと
令和元年9月12日 五瀬
先週8日、台風15号が関東地方を襲いました。
まずは、台風15号により、命を落とされた方へのお悔やみと被害に遭われた方々にお見舞いの言葉を申し上げます。
このたび関東地方を直撃した台風15号が残した爪痕は、私たちの想像(想定)を越えるものとなっています。また、8月中旬に九州北部地方を襲った豪雨など、近年日本列島の至る所で、いや世界のあちこちで何がしかの災害が起こっています。やはり、地球温暖化の影響があるのかと思わざるを得ないような状況です。
さて、台風15号関連のニュースが台風通過後も毎日のようにテレビ等で報道されています。台風が過ぎ、3日目を迎えても水や電気等のライフラインが復旧しておらず、水や食料の確保、携帯電話の不通、ガソリン補給ができないことによる移動の問題等々、市民生活に大きな影響を与えている状況が伝わってきます。また、私の前任校では、医療的ケアを必要としている子供たちがいましたので、災害弱者と言われる障がいのある方々や高齢者の方々はどのようにされているのだろうか、大丈夫だろうかという思いも込み上げてきます。
本校は、今年1月に熊本市と福祉子ども避難所の設置に係る協定書を締結しました。学校の取組としては、備蓄品の確保、防災訓練の実施、防災マニュアルの整備等、防災教育の充実にも努めているところです。
防災のための取組を組織としては進めてはいるつもりですが、実際に大きな災害が再び起きたときに、本当に熊本地震の経験を教訓として生かせるかどうかは、最終的には各個人の意識と行動に係ってくると思います。
災害は再び起こりうること、災害の記憶を風化させず後世に伝えていくべきこと、私たち一人一人が日頃から災害への備えを怠らないことを、この台風15号の教訓として学び実践していかねばなければなりません。
以下は、私自身が最近確認した主なことがらです。
□ 3日分の水と食料があるか。(学校にも備えているか。)
□ 非常時に持ち出せるものをまとめているか。
□ 車のガソリンは常に半分以上入っているか。
□ 携帯電話の充電用バッテリーの備えは大丈夫か。
□ 家族との連絡手段(方法)は確認できているか。 等
皆さんは、学校での備え、各家庭での備えは大丈夫でしょうか?
是非、確認してみてください。
「令和」時代の幕開けとともに・・・
平成31年度がスタートし、その1ヶ月後には年号が「令和」へと変わりました。今年になって2度目の正月を迎えたような気分になったのは私だけだったでしょうか!?
さて、日本中が令和元年を迎えた今年は、熊本はばたき高等支援学校の開校、盲聾の寄宿舎新築移転、そして運動場の整備等々、本校の学校環境は大きく変わってきています。そのようなときだからこそ、熊本聾学校にとっても良いチャンスと捉え、学校変革の年にしたいと考えています。
本校の子供たちにとっての教育活動を保障することは当然ですが、さらにステップアップした「魅力ある熊聾教育の創造」を目指して教職員一丸となって取り組んで参ります。今後の具体的な取組については、お便り等でお知らせしていきます。
また、保護者の皆様や関係機関の皆様にも様々な提案をさせていただきながら、PTA・関係機関と一体となり新しい仕組み作りにもチャレンジしていきたいと存じます。
今後とも本校教育活動に対しまして御理解・御支援を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
スポーツを通して学ぶとこ
最近、スポーツ界で実にいろいろなこと起きています。大学アメリカンフットボールでの危険タックル、高校バスケットボールでの審判への暴行、高校ハンドボールでの肘つき等、目を疑うような行為が次から次へと…。
そんなニュースが入る一方、サッカーワールドカップでは惜しくもベスト8を逃した日本チームでしたが、試合後のロッカールームを綺麗に清掃したうえに、感謝の言葉を残してきた彼らに世界から賞賛の声が上がりました。日本人として、嬉しくも誇らしく思えるニュースでした。
どのスポーツ競技も、勝つことをひとつの目標に頑張っていることは言うまでもありません。しかし、勝つことのみに偏った勝利至上主義が、先に挙げたような事例に繋がるのではないでしょうか。
本校には運動部活動として、陸上部・バドミントン部があります。部活動の意義を考えたとき、最終的に目指すところは「豊かな人間性や社会性の育成」です。子供たちそれぞれの体力・競技力の向上はもちろんですが、異年齢集団での活動をとおして、自主性・協調性・責任感・友情・連帯感、そして思いやりや感謝の心等々を育んでいくことが何より大切なことと捉えています。
前述のようなニュースを目の当たりにして、私たちは何のためにスポーツをしているのか、子供たちにスポーツをとおして何を学ばせようとしているのか、私たちの足元を見る機会にしたいと思います。
梅雨入り雑感
気がつけば赴任から3か月目に突入です。
昨日まで続いていた晴天の日々が一転、予報どおりの雨模様となりました。
雨の日の昼休みは、小学部の子供たちは給食が終わると遊びたい一心で一目散に体育館に向かいます。校長室のドアを開けていると、「今から鬼ごっこしに行くよ~!」と私に報告していく1年生の子。「なんとまあ子供らしい! 愛らしいことか」と思いながら、はしゃぎながら駆けていく子供たちの背を見送りました。
小学部の子供たちに限らず、幼稚部の子供たちにも、学校にいる間もっともっと思いっきり遊んでもらいたいなあという気持ちがあるのですが、なかなか叶えられないジレンマ(時間設定の難しさ)があります・・・。