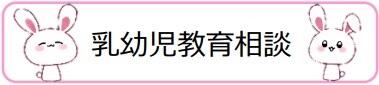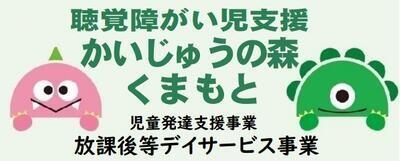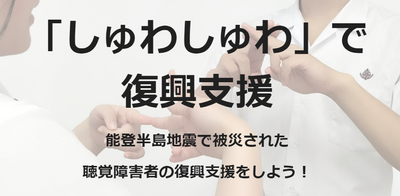校長室からの便り
今、熊聾では・・・(その244)
オンラインでの授業や会議が進められるように、2日間にわたり教職員向けの研修を行いました。
学校に派遣されているICT支援員の方を講師として、「Google classroom」や「Google Meet」等について、その概要や基本的な操作を学びました。
私にとっては、1回の研修参加では熟知するまでに程遠い感じでした。「習うより慣れよ」ということでしょう。
令和3年5月26日
熊本聾学校 校長 五瀬 浩
今、熊聾では・・・(その243)
本校卒業生のTさん、Oさんが教育実習生として教壇に立つことになります。
昨日の職員朝会で実習生に自己紹介をしてもらいましたが、二人とも緊張した面持ちで挨拶をしてくれました。
幼稚部から高等部までを本校で過ごした生え抜きの卒業生が、教師を目指してくれていることに喜びを感じます。これからの実習で様々なことを吸収し、充実した実習になることを願っています。
令和3年5月25日
熊本聾学校 校長 五瀬 浩
今、熊聾では・・・(その242)
梅雨に入り、雨の日が多くなってきました。(当然と言えば当然ですね…)
雨の日でも気分が憂鬱にならないのは幼稚部の子供たちです。3歳児クラス(赤組)の子供たち6人が、長靴をはき、傘を差し、レインコートを着て、雨の日探検に出かけていました。水たまりでバシャバシャと水を弾き、はしゃぐ子供たちを見ていると、なんとも心が和みます。
何か発見できたかな?!
令和3年5月24日
熊本聾学校 校長 五瀬 浩
今、熊聾では・・・(その241)
小国支援学校から「校歌に手話をつけてほしい。」との依頼がありました。
コロナ禍の中、歌唱の時に声を出せない状況があるため、歌詞に手話をつけることで、子供たちの生き生きした表情が見られるだろうという想いからの相談でした。現在、御依頼に応えられるよう本校数名の職員が頑張っているところです。小国支援学校の皆様、乞うご期待!もう少しお待ちくださいませ。
(手話歌作成担当の本校職員のハードルを上げたかも…)
さて、手話歌に関しては、1990年代頃に手話歌の是非について議論があったことをおぼろげながら記憶しています。手話を広めるという意味では一役買っているのでしょうが、一方で戸惑っている「ろう者」がいらっしゃることも事実です。
もともと歌詞は日本語で書かれています。それらの歌詞に日本語に対応する手話単語を単純に並べていくだけで手話歌になるかと言えばそうではないと私は思っています。手話は大きく分けると2つあります。ひとつは日本語の文法に従って単語ごとに手の動きを当てはめ、日本語を話しながら行う日本語対応手話です。本校の多くの職員は聴こえる教員(聴者)ですので、この日本語対応手話を中心に用いています。ほとんどの手話歌には、この日本語対応手話が用いられています。もうひとつは、日本手話というもので、日本語とは全く文法体系が異なる別の言語で、ろう者のコミュニティの中から自然に作り上げられてきたものです。
少なくとも私たち教職員は、この2つの異なる手話のことを知っておかないと、子供たちに正確な情報が伝わらないばかりか、全く逆の意味に伝わってしまうなど大変なことが起きてしまいます。
聴者である教員が日本手話を駆使できるようになるには、相当な努力と日本手話の環境が整うこと等々が必要でしょう。日本手話が堪能とまではいかなくとも、日本手話に敬意を払いつつ、日本手話についての学びを続けることは必要だと思います。地道に学びを続けて参りましょう。
令和3年5月21日
熊本聾学校 校長 五瀬 浩
今、熊聾では・・・(その240)
本年度の県高等学校総合体育大会は無観客で開催されることが決まりました。
本校生徒たちが関係する種目として、バドミントンは23日(日)にシングルスの試合が「熊本県立体育館」で行われます。陸上競技は今月29日(土)、30日(日)に「えがお健康スタジアム」にて行われ、本校からは100m、200m、走り幅跳びに出場します。
無観客ではありますが、試合ができることは選手たちにとっては何よりの救いです。保護者の皆様も熊聾職員も応援には行けませんが、生徒たちの健闘を祈り、エールを送りましょう!
また、県高等学校総合文化祭は形態を変えての開催となります。特別支援学校関係では作品展示が当初は予定されていましたが、取りやめとなりました。今後は他の場面を利用して、生徒たちの輝く作品や姿を発信できればと思っています。
令和3年5月20日
熊本聾学校 校長 五瀬 浩