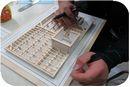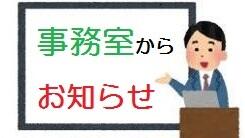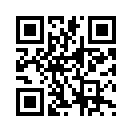建築科からお知らせ
 建築科 授業風景16
建築科 授業風景16
【建築科2年生授業】 製図
建築科2年生の授業「製図」の様子です!
現在取り組んでいる課題は、鉄筋コンクリート構造の
平面図「店舗付事務所設計図」に取り組んでいます。
尺度の感覚を養うために、製図例とは違った尺度で
作製中です!




 建築科 授業風景15
建築科 授業風景15
【建築科1年生授業】 工業基礎
建築科1年生の授業「工業基礎」の様子です!
「工業基礎」の授業では「製図」を勉強しています!
製図とは、建築空間の構想を図法や規約に
沿って図面に表します。
1年生では、製図用具の使い方から線や
文字の表現の仕方などの基本的な作製の
仕方を学びます。
現在、平屋建専用住宅の平面図を作製中です!




 建築科 授業風景14
建築科 授業風景14
【建築科4年生授業】 実習(テーマ 測量)
建築科4年生の授業「実習」の「測量」の様子です!
「測量」の実習で使用しているのは機械は
「セオドライト」です。
セオドライトは、水平角や鉛直角といった
角度を測定する測量機器で、地形測量などで
活躍しています。
据付から視準までを正確に行えるよう勉強中です!




 危険物取扱者試験(建築科)
危険物取扱者試験(建築科)
令和2年度(第2回)危険物取扱者試験
令和2年11月8日(日)に令和2年度(第2回)
危険物取扱者試験が行われました。
危険物取扱者試験は消防法によるガソリンなどの
「危険物」を取り扱う場合などに必要な国家資格です。
先日、合格発表があり
◎危険物取扱者 乙種4類
建築科1年 1名
計1名が合格しました!
 建築科 授業風景13
建築科 授業風景13
【建築科2年生授業】 実習(テーマ PC)
建築科2年生実習では、4つのテーマを
勉強していますが、その1つである「PC」
の授業です!
PCではExcelを中心に学んでいます。
テキストの例題を通して、基礎から学び、
応用的な実習問題に挑戦していました!



 建築科 授業風景12
建築科 授業風景12
【建築科3年生授業】 科学と人間生活
建築科3年生の授業「科学と人間生活」の実験
「バイオリアクターの作成」の様子です!
実験の目的は、アルギン酸の性質を利用して胞膜酵母
(固定化酵母)を作り、エタノールを生成する
バイオリアクターを作成することです。
人工イクラなどのアルコール発酵の食品に
利用されています!




 建築科 授業風景11
建築科 授業風景11
【建築科2年生授業】 実習(テーマ 木造軸組模型製作)
建築科2年生の授業「実習」「木造軸組模型」製作の様子です!
現在の作業工程は、基礎から土台、火打土台を作製し、
「大引き」から「根太」までを作製中です。
「大引き」と「根太」は、床下の部材であり、目にする機会は
あまりないですが、力を地面に伝える重要な部材です!




 建築科 授業風景10
建築科 授業風景10
【建築科4年生授業】 実習(テーマ 測量)
建築科4年生の授業「実習」の「測量」の様子です!
「測量」の実習で使用しているのは「レベル」という
機械です。レベルは、地面の高さを測る測量機器で、
測点というポイントを決め、2点間の高低差を測り、
それを繰り返すことでその土地の高低差が分かります。
学校の正門付近の登り坂を測量中です!




 建築科 授業風景9
建築科 授業風景9
【建築科2年生授業】 実習(テーマ 木造軸組模型製作)
建築科2年生の授業「実習」「木造軸組模型」製作の様子です!
木造平屋建(約50㎡)住宅の模型を作製の様子です!
現在の作業工程は、ベースの準備、基礎から土台までを作製し、
火打土台を作製中です。火打土台とは、水平面の入隅部を斜めに
結んで三角形を作り固め、風や地震などに対して建物の変形を
防ぐための部材です。




 建築科 授業風景8
建築科 授業風景8
【建築科2年生授業】 実習(テーマ 木工)
建築科2年生の授業「実習」の「木工」です!
前回までは、鋸引きの練習でしたが、
今回からは、「平ほぞ差し」という仕口部分を作製します。
墨壺、墨差し、曲尺(さしがね)を用いて「心墨」を出し、
その墨に合わせて墨付けを行います。
墨付け後には、鑿(のみ)、玄能を用いて「ほぞ穴」を
作っていきます。初めての、鑿を使っての授業でしたが
なかなか疲れた様子でした!