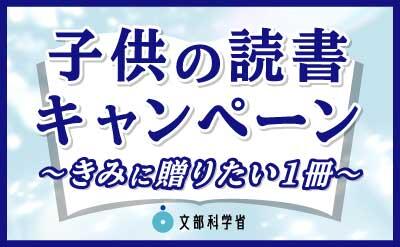銅山川の調査6 H24.7.10(火),12(木)
以前、報告したように銅山川には砂防ダムを境として水生生物や魚がいない。そこで10日は、どのあたりまで水生生物がいないのかを確かめるために川を下った。
まずは、近年整備された「あさぎり山荘」周辺。このあたりの石は、鉄分を含む赤い石が散乱している。石をはぐと、ごくまれに1mm程度の見たこともない水生生物を発見したが数は少ない。また、川底の石はヌルヌルとしていて、とても滑りやすい。なお、「あさぎり山荘」の横から銅山川に流れ込む小川があり、そこには沢ガニやアブラメの姿を確認することができた。また、川底の石はヌルヌルしていなかった。




「あさぎり山荘」から約200m下流に堰を発見し調査を行った。堰には、魚道もなく、魚は遡上できないと思われた。水生生物はヒルとカエルでここも数が少ない。川はきれいだった。さらに川を下り、八幡宮横の銅山川を調査。その途中で一本の支流と合流している。川底の石はヌルヌルとはしていないが、水生生物はヒルぐらいで、相変わらず数は少なかった。フルーティーロードを横切り、500mほど下ったところを調査したところでやっと魚の姿を確認することができた。その途中にはもう一本支流と合流しているようだ。川に降りることはできなかったため水生生物の確認はできなかったが、2本の支流との合流により、水質が変化したのではないかと考えられる。





12日には、これまでの調査結果を地図上に記録したり、文献を整理するなどして成果をまとめた。この夏休みを利用して、水質の調査を行っていきたいと思う。
まずは、近年整備された「あさぎり山荘」周辺。このあたりの石は、鉄分を含む赤い石が散乱している。石をはぐと、ごくまれに1mm程度の見たこともない水生生物を発見したが数は少ない。また、川底の石はヌルヌルとしていて、とても滑りやすい。なお、「あさぎり山荘」の横から銅山川に流れ込む小川があり、そこには沢ガニやアブラメの姿を確認することができた。また、川底の石はヌルヌルしていなかった。




「あさぎり山荘」から約200m下流に堰を発見し調査を行った。堰には、魚道もなく、魚は遡上できないと思われた。水生生物はヒルとカエルでここも数が少ない。川はきれいだった。さらに川を下り、八幡宮横の銅山川を調査。その途中で一本の支流と合流している。川底の石はヌルヌルとはしていないが、水生生物はヒルぐらいで、相変わらず数は少なかった。フルーティーロードを横切り、500mほど下ったところを調査したところでやっと魚の姿を確認することができた。その途中にはもう一本支流と合流しているようだ。川に降りることはできなかったため水生生物の確認はできなかったが、2本の支流との合流により、水質が変化したのではないかと考えられる。





12日には、これまでの調査結果を地図上に記録したり、文献を整理するなどして成果をまとめた。この夏休みを利用して、水質の調査を行っていきたいと思う。