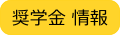 |
 |
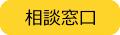 |

1学期の間は3階の音楽室から毎日のように響いていた校歌の歌声が2学期の後半以降ぱったりなくなったので、不思議に思って11月頃、担当の山田先生にそれとなく水を向けてみました。何と、「子どもたちに演歌を作曲させている」と伺い、驚くと同時に「どおりでピアノの短調のピアノのメロディばかりが聞こえてくるわけだ」と納得しました。 人生を重ねるほど、心に沁みるようになる演歌ですが、ある意味年寄りっぽいので、果たしてうちの生徒たちが食いついてくるのかと思い様子を伺ったところ、意外にも楽しそうに取り組んでいるとのこと。重ねて驚き、「作品ができ上がったら、是非発表会を行って下さい。その時は聞きに来ますので声をかけて下さい」とお願いしました。 2月27日(月)の4限目、ご案内を受け発表会を参観してきました。 (当日の様子は、山田先生が3月2日にアップされた「音楽の授業で作曲に挑戦しました!」の記事をご参照ください) 短歌や俳句のコンクールに日ごろから積極的に応募している本校生です。創作意欲の高さは知っているつもりですが、音符が華麗に舞う譜面を見せてもらっての第一印象は「これ、本当に生徒たちが作曲したの?後生畏るべし!」でした。授業中の様子や指導の苦労話、そして生徒たちは作詞も作曲も手掛けたと伺い、高2の頃「なつやすみ折句」の課題(五七五七七の頭にな・つ・や・す・みの一文字ずつを折り込んで短歌を作る宿題)ぐらいでも四苦八苦したことを思い出し、「大変だっただろうなぁ・・・」とすっかり同情しました。
可笑しかったのは、「我が冬休みの怠惰」という題の作品。苦痛の2学期が終わり、待ちに待った冬休みを満喫したものの、勉強を後回しにしてしまって、自らの首をしめていく学生をイメージした歌詞で、前半の冬休みを満喫しているシーンの中で、既にじわじわと緊張感のあるメロディで不安をあおり、後半転調して最後の2小説で「気づけばあしたは始業式」というオチに入るというものでした。また、部内恋愛をしている女子の複雑な気持ちを曲に込めたものや、伝えたいのに伝えられない・伝わらない恋の難しさを3連符に託したり、16分音符などの速いテンポを使ったりして表現した作品もありました。全体では30%が恋をテーマに曲を作っているようで、43%の百人一首同様、やはり恋は不動のテーマなのだと思いました。 その他、クラスメイトがお弁当を忘れたところを見て、「お昼の悲劇」という曲を作っていた女子グループもいて、発想の豊かさに恐れ入りました。演歌の特徴のこぶしがいい感じ出ている曲もあり、楽しい発表会でした。 ところで、紅白で演歌が流れてきたらトイレタイムという同級生が多かった小学生の頃から、なぜか私は演歌が大好きでした。高3の時に石川さゆりさんの「津軽海峡・冬景色」が流行り、その郷愁の思いや艶やかさに魅入ってしまい、「青春18切符」を使って青森まで青函連絡船を訪ねに行きました。まさに歌枕を見に行ったわけです。大学の時のサークルでは、オケ(管弦楽団)でviolin partに所属していましたが、日々の自主練の時は演奏会の曲目よりも「喝采」や「二人の大阪」、「昭和枯れすすき」といった演歌のフレーズをよく弾いていたので、回りはきっと困惑を通り越してドン引きしていたことと思います。そんなふうでしたから「演歌って何だろう?」と、歌い方や音階の使い方、ルーツみたいなものにずっと関心をもっていました。 演歌の起源は韓国の民謡にあると主張する人たちがいます。「釜山港へ帰れ」が流行しましたし、桂銀淑(ケイ・ウンスク)さんもヒット曲を連発して紅白に何度も出ました。我が国が外国文化を器用に取り入れてきた歴史を踏まえれば、韓国の民謡を耳にしたことがないけどそうなのかな・・・と思ってしまいます。 演歌の主要なテーマは言うまでもなく、海・雨・涙・酒・北国・雪・別れ・・・で、それらのフレーズの中に男女の切ない情愛や悲恋を歌い込んでいます。私、演歌のDNAは万葉の頃から始まる和歌にあるのでは?と考えることがあります。 このことに関して、名だたる作詞家や作曲家がテレビ等で、演歌の極意についてお話されている場面に時折出くわします。5千曲以上を手掛け、つい先月亡くなられた作曲家・船村徹さんが「『土の匂い』を大切にしている」と、御高説をお話しになられているのを聞いたこともあります。しかし残念なことに、和歌に関連付けた話は耳にしたことがありません。直接伺うのが早いのですが、勿論そんなチャンスもありません。なのになぜそういう思いに至るかというと・・・。 例えば、平安時代中期に成立したとされる伊勢物語24段に次のようなストーリーの物語があり、男女が和歌を交し合いながら進行します。 宮仕えをすると言って、別れを惜しみながら、男が田舎町を出ていった。女は男の言葉を信じて辛抱強く待っていた。1年が経ち2年が過ぎ、待ち続け待ちわびて3年が経った。待ちくたびれていたところへ、熱心に言い寄ってくる別の男がいる。待ち続けても帰ってこない元の男はもう諦めて、新しい男の愛を受け入れることにした。ところが、「今夜夫婦になりましょう」と約束したまさにその日に、元の男が都から帰ってきた。
帰ってきた男は「この扉を開けてください」と女性の家の扉をたたくのだが、女は扉を開けず、『あなたをずっと待っていたけれど、3年の年月を待ちかねて、まさに今夜他の男と枕を交わす(結婚する)のです』と歌を詠んで渡した。 元の男は、女の選択を責めることもなく、再婚して女が幸せならばそれでいいという思いで、自分の愛情を告げつつ身を引く覚悟で『長年私があなたを愛したように、新しい人を愛しなさい』と歌を返した。 女は元の男の深い愛情に心を動かされ、夫以外の男と結婚しようとしたことを悔やみ、『ずっと以前から私の心はいつもあなたの側に寄り添っていました』と歌を詠んだ。 しかし、結局男は帰っていってしまった。女はとても悲しくなり、男の後を追っていったが、追いつくことができずに、清水の湧き出るところで倒れてしまい、嘆き極まりそこにあった岩に、指の血で『互いに思いを寄せ合うことができないで、離れてしまったあの人をひきとめることができずに、私の身は今まさに消え果ててしまいそうです』と歌を書き、女はその場で死んでしまった。 いかがでしょう。国語教師ではないので現代語訳(意訳)はかなりアバウトかもしれませんが、この約千年前の歌のやりとり、「待つ女」、「男の虚勢」、「3年目の悲劇」、まさに演歌の世界そのものだと思いませんか? そう言えば、竹内まりやさんが作詞・作曲し、中森明菜さんが歌って大ヒットした「駅」というメロディが大変美しい曲がありました。歌詞も映画的で、日常の中に起こった一瞬の愛する男女のすれ違いを歌い上げています。歌詞の後段に「二年の時が変えたものは/・・・中略・・・/今になってあなたの気持ち/初めてわかるの痛いほど/私だけ愛してたことも」と出てきます。 伊勢物語24段の3年が「駅」では2年になっているだけで、これ、伊勢物語を本歌取り(下敷き)にして作られた曲ではないかと今でも本気で思っています。というのも「初めてわかるの痛いほど/私だけ愛してたことも」、特にここの所です。不完全な歌詞ゆえに様々に解釈されているようですが、「(あなたは)私(のこと)だけ(を) 愛して(くれ)ていた)」即ち「彼がどれだけ自分のことを愛していたか、今になって身に沁みてわかった」というふうに取れば、「本当に愛し合っていたふたりが、なぜか別れてしまったのだけれども、あの愛はお互いに本気だったんだよね。それが今は自分にも分かる」という歌になり、これは下線を引いた伊勢物語の女の返歌にある心情と哀しいほどオーバーラップするからです。「駅」が演歌なのかということは別として、深読みし過ぎでしょうか? この曲、いつ頃リリースされたのか気になり改めて調べてみたら何と、1987年(昭和62年)、国鉄が分割民営化してJRになり、私が隣の佐賀県の教員から本県に転職してきた年でした。生徒の皆さんが生まれる遥か前、今から30年も昔の曲です。当然耳にしたことはないかもしれません。でも是非、一度聞いてみる価値がある名曲です。それも(色々な歌手がカバーしていますが、やはり作詞・作曲を自ら手掛けた)竹内まりやさんのものを。歌詞のような経験をしたことがなくても、ものすごく情景が浮かんでくること請け合いです。YouTubeではこの4年間に約1,300万回も再生されているようで、切ない思いを抱きながらこの曲に浸っている人が実に沢山いることが分かります。私自身、「儚くて・悲しくて・美しいという点でこの歌に優る曲を最近聴いたことがないよね・・・」という思いでYouTubeを聞きました。 伊勢物語24段、「駅」ときたら、最後にこのことについても触れておかなければなりません。結核で早世した堀辰雄による小説「曠野(あらの)」です。平安王朝時代、美しい女が身寄りを失って零落していく様子を、優しいまなざしと雅(みやび)な文体で紡いでおり、特に最後の悲劇はまさに伊勢物語24段、「駅」の世界そのものです。 著作権が消滅した作品等を公開するインターネットの電子図書館、「青空文庫」にも全文が置かれており、ダウンロードすることで読めますし、15分もあれば読み切る短編です。画面に目を落とすのが辛ければ、コピペしてワード等に印刷してもA4用紙でわずか10枚位です。中には「堀辰雄なんて聞いたことないよ・・・」という人がいるかもしれません。でも、数年前に大ヒットした宮崎駿監督のアニメ映画「風立ちぬ」は見たことがある人も多いはずです。これ、実在の人物である堀越二郎をモデルにその半生を描いたものでしたが、堀辰雄の小説「風立ちぬ」からの着想が盛り込まれていたと知ると、きっと身近に感じるはずです。実際、映画のポスターには、「堀越二郎と堀辰雄に敬意を込めて」とありました。(余談ですが、この記事をお読みの中学3年の方は、一昨日の熊本県公立高校入試の国語で、この「風立ちぬ」から引用された文章でしょっぱなの問題が作問されていたことに気付いていますよね。モチロン、「風立ちぬ」は「風が立たない」という打消しの意味ではなく、「あっ、風が吹いた!」という意味です。36年前、グリコ・ポッキーCM曲として松田聖子さんが歌った同名の曲が、後に爆発的にヒットしたことがありました。大学3年だった当時、友達同士での「風立ちぬってどういう意味だろうね?」という会話の中で、何気に打消しで訳したところ、「あんたの文法、相当ヤバい!」と笑われたことがありました) 話を戻します。「曠野」、太平洋戦争が始まる1週間前、昭和16年12月1日に発表された古い小説のようです。でも、絶対に一読の価値ありとお勧めします。ただ、女の実家の財力だけがものをいい、経済的に自立し得ない女たちは、実家の財力と男の立身出世のみに望みを託さざるを得ない「通い婚」という当時の結婚形態、これは現在と大きく異なるものであり、内容を理解する上で背景知識として知っておく必要があります。「曠野」の女が人生を賭けたひとりの男への愛、ため息をつくこと間違いなしです。ちなみに「曠」は難しい漢字です。調べてみたら「空しい」という意味でした。 演歌の作曲発表会を聞きながら、高校・大学時代の記憶をたどり心豊かなひと時を過ごしました。ありがとうございました。 【校長】 |