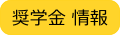 |
 |
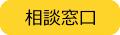 |

| 12月29日に前同窓会長の横山多喜男様から鏡餅をいただき、玄関前に飾っていました。生徒の皆さん、気付いていましたか。 お正月を迎える準備として、鏡餅を飾ることは日本古来の伝統ですが、最近は、鏡餅を飾る理由を知らなかったり、飾らないという家庭も増えているようです。鏡餅と言っても、一見鏡を思わせる姿形ではないため、「・・・?」と思う皆さんも多いかも知れません。 先日、テレビで鏡餅のいわれを説明していました。それによると、昔の鏡は鏡餅のように丸い形をしていたのだそうです。古代から、鏡には神様が宿ると信じられていたようで(そういえば、境内の御神体として鏡が祭られている神社が多いと聞いたことがあります)、お正月は年神様や御先祖様が我が家にやってくるとても大切な日であり、鏡に似せた餅を飾って神様と共に新年を祝うという意味を込めて、鏡餅を飾るということだそうです。 今日、事務室に用事で来られた育友会会長の野上様が、帰りがけに「早く鏡餅は下げとかんば・・・!」とおっしゃいながら出て行かれました。「そう言えば、今日は1月8日、松の内も昨日で終わったことだし・・・」、ということで慌てて鏡餅としめ縄を撤去したところでした。(私、供えた鏡餅を下げる「鏡開き」は1月11日とばかり思っていましたが、この辺りでは松の内で下げるみたいです。神様と共に過ごし、神様から力をいただいた縁起物ですので、ぜんざいに入れて食べたいな・・・と思いました(^^)) しめ縄は、1月15日の小正月に行われる「どんど焼き」で処分するのがよいとされています。しかし、このせっかくの地域の行事、昨今は火事と間違えられて通報され、消防車が来たとか笑えないニュースを見聞きすることもあります。この辺りではどこでやっているのだろうかと、遠い昔の小学生の頃のどんど焼きを思い出したりしました。
|