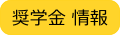 |
 |
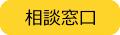 |

3年生の課題研究の発表会を、全科とも少しずつ見学させていただきました。1年間の取組を、わずか10分程度の中で後輩たちにも分かりやすくプレゼン(発表)することはとても難しかったことと思います。しっかり練習されていると感じられる班、そうでもない班それぞれでしたが、課題設定の理由、取組経過、苦労した点、感想等を上手に盛り込み堂々と発表している班が思いのほか多いように見受けました。また、バックグラウンドミュージックを小さく流したり、効果的にアニメーション機能を使って聞き手の注目を集めたりなど、様々な工夫を凝らしたものがありました。さらには、フリップの付箋紙をめくって隠れていた文字が現れるというテレビの演出を最近よく目にし、一度はそんなプレゼンをしてみたいと私自身ずっと思っていたのですが、今回そのような演出をした班もあり、高度な技法に驚きました。 3年生の皆さん。進学にしても就職にしても今後プレゼンをする機会は多いはずです。中には、会社の命運をかけたプレゼンをすることになる人もきっといることでしょう。そういう良い点はどんどん取り入れ、プレゼンの技に磨きをかけていってほしいと思います。御指導いただいた先生方には大変お世話になりました。
ところで、どういう文脈だったか覚えていませんが、幸福論を扱った本に「日本人は課題を見つけそれを解決するための取組を行うことに幸せを見い出す民族である・・・」との一文を読み、思わず「そうだよね!」って頷いたことがあります。 その一文を念頭において、平成12年度から段階的に始まった学習指導要領で小・中・高校に入ってきた「総合的な学習の時間」(専門高校では「課題研究」で代替)のねらいを改めて読み直してみます。
横断的・総合的な学習や探究的な学習を通して,自ら課題を見付け,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに,学び方やものの考え方を身に付け,問題の解決や探究活動に主体的,創造的,協同的に取り組む態度を育て,自己の生き方を考えることができるようにする。
何と小・中・高校同一文言で、課題を解決する中で身に付けた能力を、自己の生き方を考える態度まで繋ぐことを期待しています。なるほど、それがうまくいけば、その達成感に人は喜びや幸せを感じるんだろうな・・・、そう言えば不屈の闘志で様々な困難を解決していった無名の男たちを扱ったドラマ、プロジェクトXも凄い視聴率を集めていたな・・・と、漠然と納得してしまいます。
話は変わりますが、本校生の多くが就職する製造業の生産現場では、「カイゼン」活動が活発に行われていることを見聞きしている人も多いはずです。いわゆる「改善」のことで、作業効率の向上や安全性の確保などに関して、現場の作業者が中心となって問題点を見つけ、知恵を出し合いその解決をはかっていくものです。この概念は海外にも「kaizen」という英単語で広く普及し、とくにトヨタ自動車のカイゼンは有名で高く評価されています。 活動内容としては、3年生の皆さん方が1年間取り組んできた課題研究のイメージで捉えてもらっていいかと思いますが、課題研究ではそれほど強く言われなかったかもしれないことが一つだけあります。それは、どれだけのコスト削減に繋がったか、即ち結果を数字で表現するなど定量的であることが求められることです。 私自身昔、ものづくり企業に勤めていたことがあります。手元にわずか残っていた当時の資料にカイゼンの進め方が載っているものがありました。この手順はある意味、普遍的なものであり、課題研究でも同様なプロセスを踏んでいるはずです。入社を控えている3年生の皆さん方のために参考までに載せておきます。
問題提起(違和感即ち問題意識を感じる)→問題確認(問題を具体化・定量化し解決すべき問題を明確化する)→目標設定(問題が解決された状態を暫定的に決め、その測定手段を明確化する)→原因分析(問題の原因を特定)→改善策立案(原因を除去する解決策を複数立案)→改善策評価(複数の解決策から1つの解決策を決定)→実行計画作成(解決への段取りを考える)→実行(解決策を段取りに沿って進める)→評価(解決状況を評価し数値化する)
脅(おど)すつもりはありませんが、企業に入ったら勤務時間の内外を問わずこの「カイゼン」活動にかなりの時間を割かざるを得ないことが多いにありえます。特にプレゼンの前は、遅くまで残って練習をすることもあるはずです。職場の班単位で競うことが多く、指導役の班長さんがハッスルして若い社員を鍛えます。社長賞とか部長賞とか懸っていることも多く、報奨金まで出るので熱が入るのです。何歳になっても大変です!
そういうことで、企業在職中にカイゼン活動の経験があるからでしょうか。課題研究の発表会を聞いていると、ついこのような感慨に耽ってしまいます。それは・・・、加工貿易(原料や半製品を他国から輸入し、それを加工してできた製品等を輸出する貿易の形態)で立国することが宿命づけられた我が国の産業界(製造業の経営者たち)の要請で、カイゼン活動のための経験値獲得を期待されて、「総合的な学習の時間」などが学校に導入されたのではないかという思いです。深読みし過ぎでしょうか? 【校長】 |