学校概要
学校の位置
〒862-0953 熊本市中央区上京塚町5番1号(くまもとしちゅうおうくかみきょうづかまち)
(東経 130.747度 北緯 32.792度)
校地・校舎面積
校地 129,958m2
校舎 27,655m2
第一体育館 4,158m2
第二体育館 1,911m2
その他 3,351m2
教育綱領
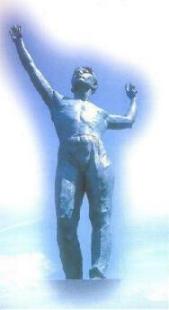 |
|
校歌
作詞 八波 則吉
作曲 永井 幸次
一、
山は大阿蘇 地軸揺りて
大空焦す 久遠の神火
川は白川 昼夜別たず
清流滔々 巨海へ放る
大なり山河 我等の揺籃
二、
工は惟精 朝夕に
工夫を凝らし 衆知を集め
学理実習 極め尽して
躍進日本の 基を成さん
壮なり雄図 我等の願望
【校歌の演奏をお聴きいただけます。こちらから->同窓会のページから外部リンクへ進んでください。】
学校のあゆみ
明治31年 4月 熊本県工業学校として創立
明治34年 6月 熊本県立工業学校と改称
昭和23年 4月 熊本県立工業高等学校と改称
昭和26年 4月 熊本県立熊本工業高等学校と改称
昭和35年 4月 定時制を創設
平成20年11月 創立110周年記念式典挙行
平成22年11月 定時制創立50周年記念式典挙行
平成30年 3月 全日制第70回、定時制第55回卒業式
平成30年11月 創立120周年記念式典挙行
卒業生総数 45,278名(令和5年(2023年)3月1日現在)
学校沿革の大要はこちら-> gakkouenkakunotaiyou.pdf
設置学科と募集定員
※学科名の背景色は、科のシンボルカラーです。
| 学 科 | 機 械 |
電 気 |
電 子 |
工 業 化 学 |
繊テ |
土 木 |
建 築 |
材 料 技 術 |
イ ン テ リ ア |
情 報 シ ス テ ム |
計 |
| 全日制 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
| 定時制 | 40 | 40 | 40 | 120 |
※全日制課程では、前期選抜と後期選抜があります。
※定時制課程では、後期選抜と同じ日に選抜を実施します。
スクール・ミッション(社会的役割)とスクール・ポリシー(3つの方針)
(全日制)教育目標
(全日制)いじめ防止基本方針
熊本県立熊本工業高等学校
〒862-0953
熊本市中央区上京塚町5番1号
(地図)
TEL(全日制)
096-383-2105
TEL(就職)
096ー382-1800
TEL(定時制)
096-383-0310
FAX
096-385-4482
URL:
https://sh.higo.ed.jp/kumakoths/
E-mail:
kumamoto-th@pref.kumamoto.lg.jp
熊本県教育情報システム
登録機関
管理責任者
校長 野崎 康司
運用担当者
HP担当者

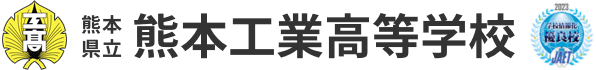
 在校生
在校生 受験生
受験生 卒業生
卒業生